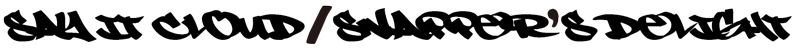Writing is dancing. Dancing is writing.
テクストは文書であることを必要としない。「テクストは書かれたもの(エクリ)であることを必要としない」と克明に述べつつ、彼[ピエール・ルジャンドル]はさまざまな文化の口承、ダンスやその振付をあげている。 だから彼は「黒人の偉大なるダンス」はそのままテクストの操作であり、ゆえに彼らのダンスはそのまま法的・哲学的・規範的に思考することそのものなのである、と事も無げに述べることができたのだ。 いわく、「ダンスはまた、それによって主体の身体が〈法〉を反響するものであって、このテクスチュアリティの外には書き込まれることはありえない」。 そう、われわれはすでに見てきた、われわれ自身がイメージであり、テクストであり、エンブレムなのだと。ならば、ダンスはそれを習得し、鍛練し、練習し、揺り動かし、舞い、跳躍させ、回転させ、軋ませ─つまり「思考する」ことそのもの以外の何かではない。だから、その振付を案出し「新しいダンス」を編み出すことも含めて、ダンスは哲学的あるいは法的なテクストを読み、註釈し、書き換え、新しい概念を産み出すこととなんら変わるところがない。だから、「ダンスを根本的な政治的操作の外にあるものとみなすのをやめなくてはならない」。 ダンスは「肉体的」で「感覚的」で「美的」なだけのものではない。ダンスを論ずるとなると、どういうわけか美術史家も人類学者も「宇宙との鼓動に一体となる」「原始的な身体感覚」などということを喋々しがちだ。だが、ルジャンドルのダンス論にあっては、イメージも言語も「越えた」原初的(プリミティヴ)な身体感覚などというものを拠り所にするような思路は、全く問題になっていない。彼は言う、「ダンスの身体が美しいのは、それが製造されたものだからである」 と。だからこそ、それはひとつの社会の、ひとつの文化=崇拝のテクスト性のなかで法的で政治的な力を持つことになる。いわく、「諸身体はシステムのエンブレムになる、そしてそこで信仰が組み立てられるのだ。ダンスは政治的である。なぜならダンスは通常の振る舞いの取り扱いを提起するからであり、主体を閃光のもとにはっきりと見せる(eclater)からだ」 かくして、「〈法〉と一緒に、ひとはダンスしにやって来るのだ」。 〈法〉との、〈テクスト〉との熱狂的なダンス。テクストとは、そしてテクストの営みとは、すべてこれ以外の何ものでもない。逆に言えば、われわれの読みまた書くこともまた「熱狂的なダンス」なのだと、いまさら繰り返す必要があるだろうか。歌、音楽、詩、絵画、つまり芸術。これらはすべて以上のような意味でテクストであり、政治的ダンスである。われわれは既に十分語った。旗なしに、ダンスなしに、歌なしに、エンブレムなしに、音楽なしに、イメージの上演なしに、社会が統治されることなどないと。次の重要な論点に移る前に、念を押しておく。ルジャンドルはここでも極めて冷徹である。「ダンスと軍楽隊による大衆の祝祭、これはまたファシストのものでもあるのだ」 と指摘し、「共産主義の儀礼性の研究の欠落」 を難じる彼は、このような非文書的なテクスト性による儀礼的な統治について、楽観的なことを一言も口にしていない。これは要するに、独裁者の儀礼の「マス・ゲーム」でもあるのだから。ダンス、音楽、詩と言っただけで、何か肯定的なものが語られていると思うのはお門違いである。彼は、まさにダンスを挙措の調教の水準に位置づけ、「古代のダンスの道徳の上に、ダンサーではない人々においても、産業への服従の一部分は構築されている。つまり、工場奴隷は姿勢と所作の合法性から利益を得ているということだ」 とまで言ってのけるのだから。つまり、「工場奴隷」は、規則正しく時間割どおりに上司の言うとおりに「踊る」ことを「調教」され「強制」され、その服従の代金として僅かな賃金を得ているのだ。言ってみれば、絵画、ダンス、音楽、歌、エンブレム、バッジの美しい演出が、すなわち身体的な調教としての政治的な操作が存在することは厭でも否み難く避けられない事態なのであり、むしろそこから始まるのだ。(拙著『定本 夜戦と永遠』(河出文庫)、東京大学博士論文、第五章第四十四節より。)
関連